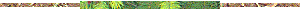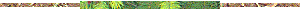
物質 matter
最終更新日:2002年05月10日 船戸和弥のホームページへ
哲学事典(森 宏一編集、青木書店 1981増補版)(p405)から引用
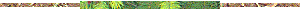
弁証法的唯物論では、意識とは独立に存在し、われわれの感覚の源泉であり、感覚を通じて意識に反映される、客観的実在をいう。それは本源的第一次的存在であり、無限かつ永遠である。自然および社会のこのうえなく多種多様な事物・過程は、運動を永遠の存在様式として空間と時間とを存在形式とするこの統一的物質の、もろもろの存在形態である。この意味でエンゲルスは、<世界の現実の統一性は、その物質性にある>(《反デューリング論》)と述べたのである。こんにち、われわれは、現代自然諸科学の成果の哲学的一般化にもとづいて、素粒子-原子核-原子-分子-巨視的物体-星-銀河-銀河団―超銀河系という無機的物質の諸階層の系列(素粒子と銀河系とが、それぞれこの系列の終点をなしているというわけではない)、および、分子―生体高分子―細胞―植物・動物―労働する人間とその社会という有機物質の諸階層の系列を、物質的に統一された世界のうちに認識するにいたっている。哲学の歴史をみると、世界の物質的統一性というこの思想が、古代ギリシアの自然学者たちにすでにあったことがわかる。すなわち、かれらのいわゆるフュシスは、みずから運動し変化する物質であり、不生不滅のものであった。西洋哲学は、こうして、じつに唯物論的世界観として出発したものである。古代最大の哲学者アリストテレスも、物質恒存の見地をまもり、生成・運動の理論の確立に努力した。ローマの原子論哲学者ルクレティウスが、<なにも無からは生じない><なにも無へと滅びない>を自然の二つの根本原理としたのは、特筆に値しよう(19世紀に確立された<エネルギーの保存との転化>の法則は、すでに古代哲学において獲得されていたこの見地の自然科学的表現にほかならないのである)。この見地に対して、キリスト教の教父哲学において<無からの創造>説が形成され、唯物論対観念論という哲学上の根本的対立が、きわめて鮮明な、両見地の対立というかたちをとることとなったわけである。近世の機械的唯物論では、有機的生命の世界をも、人間の意識の世界をも社会生活をも、物理的自然界と同質的に取り扱い、この諸領域を一貫して古典力学の諸法則で説明しようという企てがおこなわれた。物質に機械的運動しかみとめられていないなかったことになる。その後、弁証法的唯物論は、こうしたせまさを克服して、自然・社会における運動・変化・発展の理論を解明するのに成功したのである。そして、19世紀から20世紀にかけて、かつて不変と考えられていた原子も変化することがわかり、原子が物質の究極の単位だという観念がくずれるという<物質は消滅した><だから唯物論は打ち破られた>と宣伝したとき、レーニンは、はじめにしるした客観的実在としての物質の哲学的概念を明確にしめして、これと、そのつどの自然科学的物質概念とを区別しなければならないことを説き、観念論を徹底的に打ち負かしたのであった。